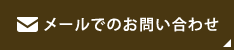認知症の人が作成した遺言書でも効力は認められますか?
A
1 遺言能力

遺言をするためには、遺言能力が必要ですが、原則として、15歳に達した者には遺言能力が認められます(民法963条、961条)。
遺言能力とは、遺言をする際の意思能力をいいます。具体的には、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識し、判断する能力です(民法963条)。
遺言能力を欠く者の遺言には、効力が認められません。
2 遺言能力の有無の判断

遺言能力の有無については、遺言者の精神的な障害の有無・程度のみならず、遺言者の遺言書作成当時やその前後の言動、遺言内容が簡明か、遺言事項が重大か、処分する財産が多額か、遺言者と取得者との関係等、周辺の事情等を総合的に判断すべきものとされています。
例えば認知症や精神的障害がある遺言者による遺言であっても、それだけで遺言の効力が否定されるとは限りません。
3 裁判例

⑴ 遺言を有効とした事例(東京地裁平成19年3月8日判決/平成15年(ワ)第15146号)
この事案では、遺言者には認知症の症状がありました。また、問題となった遺言は、過去に遺言者が作成した数通の遺言書とは異なる内容でした。
しかし、認知症の程度が重度ではなかったこと、遺言者自身が、遺言内容を変更するに至った理由(当初全財産を譲ることにしていた者に対する不信感が生じたことなど)を明らかにしており、その理由が合理的といえること、遺言書作成後も、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや誰に相続させるのが適切か等について話をしていたことから、裁判所は、遺言者が意思能力を有している状態で遺言書を作成したと認めました。
⑵ 遺言を無効とした事例(東京地裁平成5年2月25日/判例時報1476-134)
この事案では、遺言者が、脳梗塞に罹患しました。そして、その後、ほぼ同じ内容の遺言書を別の時期に1通ずつ作成しました。
しかし、1通目の遺言書作成の約4か月後で、2通目の遺言書作成の翌日の時点における医師の診察において、「どれが眼鏡か」といった簡単な質問にも答えらず、「手を挙げて」などの簡単な指示にも反応できませんでした。また、2通目の遺言書作成の約1か月後、禁治産宣告の調査のため家裁調査官が遺言者を来訪した際も、遺言者は全く言葉を発することができませんでした。
このような事情の下で、裁判所は、遺言能力を否定しました。
⑶ このように、裁判所は、遺言書作成時やその後の遺言者の病状、遺言の内容、遺言の理由や経緯等、さまざまな事情をもとに、遺言者の遺言能力の有無を判断しているといえます。
4 後の争いを避けるために

⑴ 認知症の患者で、後見開始決定がされている場合
後見開始決定がなされ、遺言者が成年被後見人である場合、遺言者は、意思能力を回復している間であれば単独で有効に遺言をすることができます(民法973条1項)。ただし、医師2人以上の立会いが必要で、かつ、立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し、署名押印しなければなりません(民法973条2項本文)。
⑵ 認知症の患者で、後見開始決定がされていない場合
たとえ認知症と診断されていても、軽度や中度の場合などで、自ら遺言の内容を決定するに足りる能力を十分に備えている場合には、通常どおり遺言書作成の手続をすることになります。
このような場合には、例えば、
・ 主治医に知能検査を実施してもらう
・ 遺言の内容を協議する際、遺言書を作成する際の遺言者の様子を録音する
・ 遺言の内容を協議する際、遺言書を作成する際の遺言者の様子をビデオ撮影する
などしておくことも、後の争いを防ぐため有効となり得ます。
より詳しいことについては、一度相続に詳しい弁護士に相談してみてください。
事務所情報
-News&Topics、Access-
 高崎事務所
高崎事務所
YKビル1階 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そばです。
【無料駐車場完備】
お車でお越しの場合
● 関越自動車道 前橋ICより 約7分
バスでお越しの場合
● JR高崎駅より
関越交通渋川行き・・・小鳥停留所下車 徒歩約3分
群馬バス箕郷行き・・・続橋停留所下車 徒歩約1分
ぐるりん・・・第一病院前下車 徒歩約2分
電車でお越しの場合
● JR信越線 北高崎駅より・・・徒歩約15分
● JR上越線・両毛線
高崎問屋町駅より・・・徒歩約20分
 前橋事務所
前橋事務所
MSビルディング前橋問屋町 201号
【無料駐車場完備】
お車でお越しの場合
● 関越自動車道 前橋ICより 約5分
バスでお越しの場合
● JR前橋駅より
前橋吉岡線/問屋町二丁目停留所下車 徒歩約5分
新前橋駅西口線/問屋会館前停留所下車 徒歩約6分
電車でお越しの場合
● JR上越線・両毛線 新前橋駅より・・・徒歩約20分